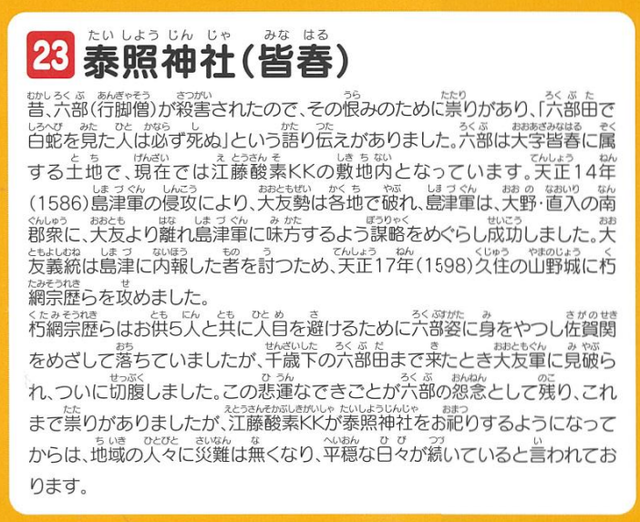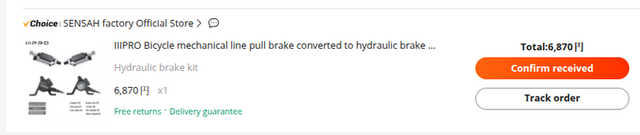今日も10時頃出発。下はデイリーユースのドライタイプ半袖ティーシャツのままでスタートしたが、アンダーなしでもよかったかも。戸次経由で宮河内の新規と鶴崎、松岡方面の拾遺。
- 阿蘇神社(宮河内)
- 水神の塔(宮河内杵河内)
- 宮谷天神社
- 天満神社(宮河内新田)
- かきから天神社
- 若宮八幡社(南)
- 常行神社
- 八坂神社(猪野)
- 若宮八幡宮(森)
- ランチ
- 愛宕社(南鶴崎)
- 天満社(家島)
- 大村稲荷神社
- 泰照神社
- 帰路
- まとめ
- ブレーキコンバータ発注
阿蘇神社(宮河内)
R10を白滝橋南詰めで左折して土手道を進み、県道48号を進み、下戸次大内深追の天満社を過ぎた先に阿蘇神社。






縁起。阿蘇の阿蘇神社から大野川を下って鎮座したと。宮河内(インターチェンジがある)の名称もこの神社が由来と。

水神の塔(宮河内杵河内)
GoogleMapsで発見。鳥居マークではないけど行ってみた。

縁起。罔象女命に「みずはめのみこと」とルビを振っているけど、「みず(づ)のはめ」 が一般的なもよう。


ミヅハノメ - Wikipedia
いったん次の天神社に行って、再度前を通ったら後ろにも碑があるのを発見。とういか、見落としていた。表には「罔象女」、裏には文政10年(1827年)の刻。



宮谷天神社
宮谷の集落の奥に宮谷天神社。おお、グラベル。「でも道なかったん?」と思っていたらその先で離合の難しそうな道幅の旧道に合流した。

若宮八幡社(南)
乙津川の対岸だが、大きく回って高田橋を渡る。
森バイパスを通っているときから対岸の鎮守の森と社が見える。

縁起。若宮八幡宮なのでやはり大友能直の勧請で、薩摩藩に焼かれたと。丸亀は当地の上流南東方面。

社務所兼宮司住居と思われるところの一角の井戸はなんか聖性ありそうな屋根付き。

左手は駐車場ではないようだけど、境内につながっている。お祭の時に使うとかかな。

いまどきのやつ。

見たら2日前が例大祭だった。
八坂神社(猪野)
県道まで戻って、西に進んで、ちょっと登って八坂神社。ここも広い。二の鳥居は嘉永元年(1948年)。




縁起。大分君稚臣が出雲神を勧請したとあるが、いつどういう経緯で八坂神社になったのかが書いてない。

拝殿右手の稲荷社。拝殿には天井画。倉稲魂神に加えて、保食神、猿田彦大神も祀られている。




その右に大分のお約束の天神社。拝殿に天井画・書。ペコちゃん風の人も見える。どこかから遷座してきたのがうかがえる。





一の鳥居から県道を挟んだところに日清露戦役記念合碑。以前は境内だったんだろう。

北西角に掲示板。縁起も書いてあるけど、「いつどんな経緯で八坂神社になったのか」は不明のまま。



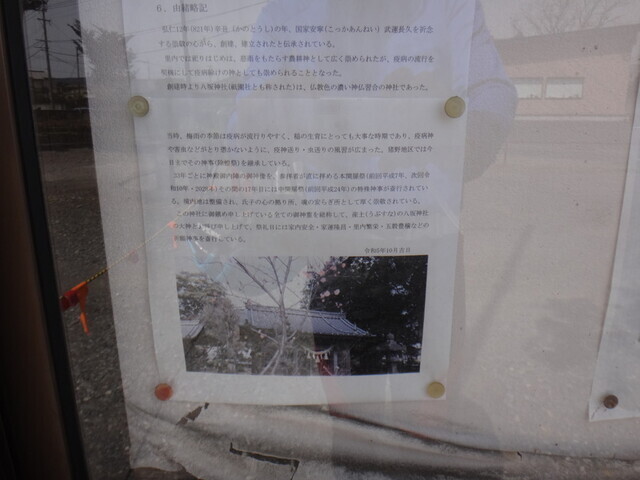
新宮総代体制がうまく機能していないらしい。ほぼボランティアだろうし、ご苦労さまです。宛先は「猪野三区 自治区在住者 各位」。ここでは猪野八坂神社の社名。

若宮八幡宮(森)
森町バイパスまで戻って、北東方面に若宮八幡宮。周辺に若宮を掲げる施設やアパートがある。小字なのかどうかは調べがつかなかった。




縁起。移転を余儀なくされ、合併して森天神社の敷地に社殿を移築したとか。でも鳥居や拝殿の扁額には「若宮八幡宮」としか表示されていない。

森天神社記念碑。社殿はなくなっても祭は継続していると。合併時に摂社的に残せばよかったのに。


なおこのあたり、大字森、大字森町、大字のつかない森町西1丁目〜5丁目がある。森町西ができたのは令和2年(2020年)。
水神塔。境外かもしれない(ブロックが境界線っぽく置かれている)。

ランチ
マルミヤストア鶴崎森店でスーパーアゲアゲランチ。イートインスペースはあるが椅子が撤去されているというわけのわからん状態。コロナ対策を戻してないのかも。ベンチも他の方が長居していたので地べたでいただく。

愛宕社(南鶴崎)
前回の鶴崎神社探訪の時は認知していなかったけど、振り返りをしていて存在を認識した。江戸時代の鶴崎の中心地付近。


大村稲荷神社
いったん40m通りに出て、鶴崎泊地を渡り、野坂神社の西側を行っていくと、放送塔発見。近づいてみると大村公民館。山車庫らしき建物もある。この裏側やろうなと細い道を入っていく。

両脇に公園。こういうケースだと端っこに映されるケースが多いけど、ここは中央に。もともとの位置なんやろうな。




マピオンには「大村小社」とあるけど、固有名詞ではなさそう。
泰照神社
桃園歴史マップでプロットして、前回訪問予定だったのに見落としていた。
地図の場所に入ってみるけど、江藤酸素の工場しかない。スマートフォンで確認したら江藤酸素の敷地内とな。